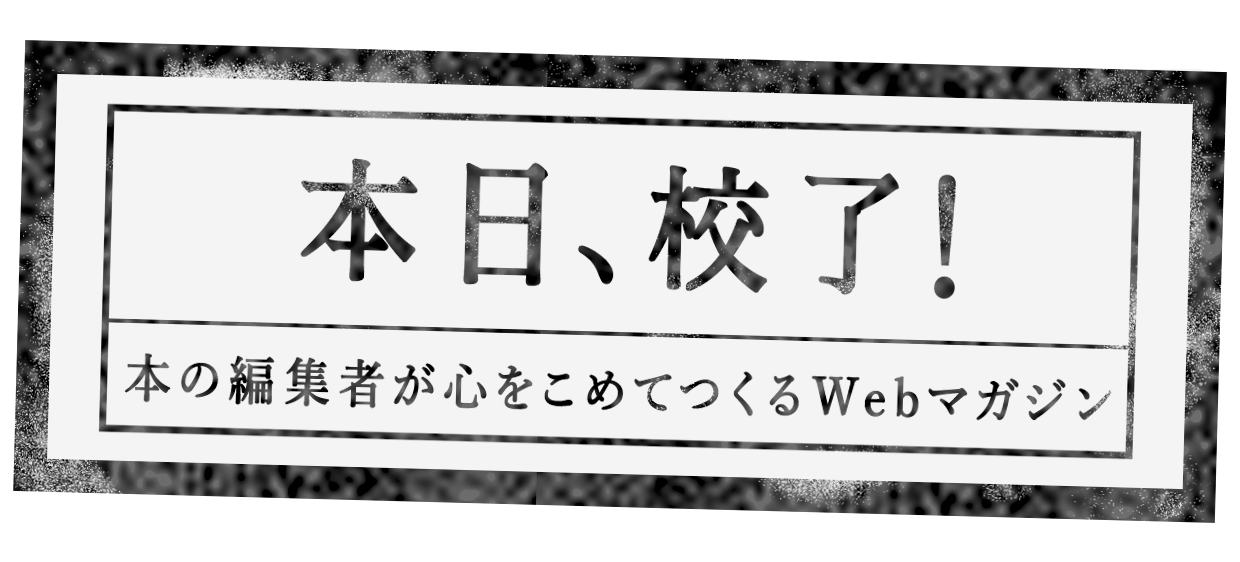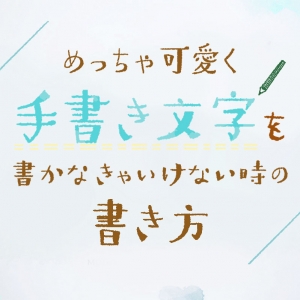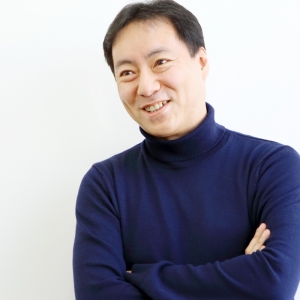【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第3回 「書籍編集はボクシング。作家はボクサー。編集者はセコンド」
Category: あう
第10回 本屋大賞にも選ばれ、2016年には岡田准一さん主演で映画化もされた小説『海賊とよばれた男』。ハードカバー、文庫あわせ420万部という大ヒット作を手掛けたのが、編集者の加藤晴之さんです。
インタビュー第3回目の今回は、加藤さんが『白洲次郎 占領を背負った男』をヒットさせたあとの話。「さあ、書籍編集者でがんばろう」と思っていた矢先に、まさかの古巣『週刊現代』からの召集令状が届いて……。
加藤
召集がかかって、2006年に52歳で『週刊現代』の編集長になって。2年間やって訴訟の山を築いて。名誉棄損の損害賠償請求額で、合計すると30億とか40億円くらいになったと思います。
谷
40億! ちょっと気が遠くなりそう……。
加藤
でもその額は請求されただけで、実際に判決が下って会社が払ったのはたいした額じゃないと思ってたら、結構払ってるんですよ。会社に大損させたわけです。もちろん、勝った裁判もあるのですけど。ちょっと言い訳がましいですけど、日本の裁判所というか、司法って、三権分立してないというか。裁判官ご自身の出世というか、人事を気にして、スキャンダルをおそれる政治家や官僚にすり寄ってといったら偏見かもしれませんが、判決がメディアに厳しくなってる傾向があるんですね。しかも事実の立証責任が、原告でなく訴えられた側にある。それで、SLAP訴訟(高額訴訟)といって、メディアを恫喝する傾向があるのは、週刊誌にかかわる人なら誰もが感じているところじゃないですか。裁判に縁のないみなさんは、日本の裁判は公明正大だと思われているけど、けっこう生臭いとこあるんです。
中野
そうか、メディアに厳しい判決が……。結局、その損害は白洲次郎の利益でまかなえたんですか?
加藤
利益で換算すると全然、赤字を埋めるには届かないですよね。『海賊とよばれた男』を出せてなかったら、とてもじゃないですけど、円満に定年退職なんてとんでもなかった。
中野
背水の陣で挑んだ。
加藤
いえ、そんなことは考えてなかったけど、結果的に、『海賊とよばれた男』がなかったら、大変でした。
中野
これでペイできてるのってすごいですよね。
加藤
まあ、そんな感じだから、『週刊現代』も、また「はい、クビ」みたいな強制終了。
中野
じゃあ、書籍に行ったら、また地獄に戻った感じでした?
加藤
いや、そうじゃなかった。
谷
えっ、なんでですか?
加藤
それは、時代の変わり目を感じたからです。というのは、98年からの『フライデー』編集長のときに、もうすでにネットの風圧を感じていたんです。日本のインターネットが本格的に普及し始めるのが、たぶん95年の「阪神淡路大震災」「オウム事件」の年で、それから3年後の時点で、フライデーが撮った写真が、ネットに勝手に上がってしまう、とかあって。
谷
そっか、ネットが出てきたから。
加藤
もともと、『Fridayフライデー』は、新潮社から81年に創刊された『FOCUSフォーカス』の後追い雑誌として84年、創刊部数が70万部でスタートしたんです。写真週刊誌という『フォーカス』が切り開いた新ジャンルの市場が、あっという間に急成長したから、講談社だけでなく、雑誌を発刊する出版社がみんな参入した。“写真週刊誌バブル”。80年代は、たとえば「三浦和義ロス疑惑」とか、「豊田商事事件」とかってあったじゃない? 写真週刊誌やワイドショーが過熱、一億総探偵みたいな時代だった。
谷
あっ、豊田商事事件の映像、大学の授業で見ました。マスコミが見てる前で殺人が行われた……。
加藤
テレビのワイドショーが「犯人を追う」というか、「あ、いま三浦さんが〇×しました」って、まだ容疑者にもなっていなのに追いかけまわして盛り上がってた。人権も何もあったもんじゃない。これは今はもうナシでしょ、って思うんですけど。
もともと写真って強烈なインパクトがありますよね。アメリカの『ライフ』とか写真をメインに扱ったグラフ誌があって、そこで活躍した戦争・報道写真家として有名なキャパや、ベトナム戦争報道の沢田教一さんとかが、戦争現場の生々しい現実の決定的瞬間を切り取った写真を覚えてる人は多いでしょ。いまではインスタや動画をスマホで誰もが撮って、世界中に配信できるのだからビックリだけど。
3FET(さんえふいーてぃー)ってわかる?

一同
わかりません。
加藤
3Fは、『FOCUS』新潮社、『Fridayフライデー』講談社、『FLASH』光文社。ETっていうのは『Emma』文藝春秋。『TOUCH』ってのが小学館。
谷
『Emma』と『TOUCH』って知らない……。
加藤
3FETって、雑誌で経営基盤を築いてる大手出版社が全部参戦したのね、マックスのとき。写真週刊誌マーケットが400万~500万部ぐらいあったんじゃないかな。それが一番のピーク時でしたね。
中野
毎週ですからね。すごい。
加藤
それが、あっという間に萎んでいくんですけどね。86年の「たけし事件」って、たけしさんが講談社に殴りこんできちゃったフライデー襲撃事件が引き金になって。それまでの「一億総探偵」時代の気分が、イッキに冷えて、写真週刊誌ってやりすぎじゃないか、みたいに潮目が逆流、写真誌バブルがはじけてしまった。最盛期5誌あったのが、エンマ、タッチが脱落して3F、フォーカス、フライデー、フラッシュが残ったものの、フォーカスも2001年に休刊。
僕が『フライデー』の編集長をやったのが98年から2000年。インターネットが本格的に日本でも商業的なベースになってくる元年がたぶん「阪神淡路大震災」「オウム事件」の95年。Windows 98とかができてインターネットが台頭して……。当時はまだ「iモード」のころで、インターネットの縄文時代みたいな感じですけど、それでも『フライデー』の毎週作った手ごたえがネットに押されつつあった。メディアとして雑誌はこれからヤバい、大変な時代が来るというのは肌で感じてたんです。
谷
iモードとか懐かしい!
加藤
実はフライデー編集長の最後のころに、「iフライデー」(iモードのネットニュースメニューに上げて課金する)を出そうとして開発を始めてたんですけど、僕のあと3年後くらいにサービスが始まったのかな。
そこで、話は戻るけど書籍に行くなんて地獄に落ちたかなと思ったら、こっちは天国かもって。それなのに、「召集令状」がきて、天国(書籍)から地獄(雑誌)に行け、と。で、また書籍。天国じゃないけど、かといって地獄でもない甲本ヒロトみたいな生活。
谷
甲本ヒロト(笑)
加藤
ちょっと遠回りしましたけど、書籍編集セクションを経験して、雑誌の世界を横目で見られたから言えたのかもしれないけど、これから出版界では、メディアとしての雑誌はきびしくなると思ったのね。雑誌は相当辛くなるだろうと。ニュースエンタテインメントメディアである雑誌が、デジタルメディアにとって代わられることからは、逃れられないだろうと。
池田
速報性で勝てないですもんね。
加藤
そう。しかも雑誌の編集者っていうのは、関わり方がチームプレーですよね。アメリカンフットボールが一番近いと思うんだけど、いろんな役割をになって、立案した作戦をそれぞれの立場で実現していくみたいな。それだけいろんな人が関わりながら取材して撮って書いて編集してつくっても、結局、「はやい」「やすい(タダ)」「便利」なデジタルメディアに勝てそうもないなっていうか。紙メディアが一生懸命作ったのをタダで流すのはどーよ、と思ってたらスマホが登場して、あっという間にニュースに触れる習慣が紙からネットに変わってしまった。一方、書籍の場合は同じ編集者でも違うんですよね。スポーツでたとえると、書籍はボクシングっていうか。
中野
おもしろい。
谷
たしかに。ボクシング。
中野
1人だもんね。
加藤
作家がボクサーで、われわれ編集者がセコンドというかトレーナーというか。『ミリオンダラー・ベイビー』で言うところの、クリント・イーストウッドとヒラリー・スワンクみたいな。『あしたのジョー』で言うと丹下段平みたいなブサイクもいますけど。そういう関係なんで、あ、編集者として勝負ができる、戦いになるなと思ったの。書籍はね。

谷
じゃあ、比較的前向きな気持ちだったと。
加藤
そう、あれ、ここ天国じゃんって、前向きな気持になってたわけ。そんなときに「雑誌に戻れ」っていう召集令状でしょ。また天国から地獄ですよ。「えー!?」と思って。このあたりいい加減なんですけど(笑)。
池田
95年で、インターネットのことをすでに脅威に感じていたというのは、会社全体もそういう雰囲気があったんですか?
加藤
いや。95年っていうのは阪神淡路大震災とオウム真理教事件でしょ。あの頃から徐々に変わりつつあったんですけれど、僕らは気づいてなかったんです。もう、雑誌をガンガン売ってたからね。実際に『フライデー』の編集長だった98年から2000年も、ネットから吹く逆風は感じてたけど、まだまだ紙メディアは元気だったし。その後、徐々にデジタルメディアのほうにお客さんが流れ込みはじめていって。
最終的なメディアのパラダイムシフトというか、既存のメディアが一般読者を情報で振り回す「天動説」が、一般の人たちがメディアを振りまわす「地動説」にとってかわられるのは、iPhone、スマホが一気に普及してからで、気が付いたらあっという間に環境が変わっていました。
一方、書籍っていうのは、負けるときは1対0で負ける。つまり、失敗したって、初版の5000部とか6000部が回収できないくらいで。でも、勝つときは100対0で勝てるんですよね。だから、販売(マーケティングとセールス)さえしっかりしてれば、意外とリスクは少ないんです。
中野
希望がある言葉をもらった。
加藤
これからは書籍編集者のほうがいいんじゃね? と思って。もうちょっと修行しようかなと思ったら召集令状がきちゃって。『週刊現代』の2年で訴訟の山を築いて、またさまようわけです。
谷
そう思っての、第二次書籍編集時代のスタートですね。
中野
ふたたび書籍に戻ったあとに最初に出されたのは?
加藤
最初は、デアゴスティーニみたいな、パートワークを開発・発行する仕事をしました。
中野
あ、毎週送られてくるやつですね。
加藤
そうです。定期的にパーツが送られてきて、ちょっとずつ、戦艦大和とかフェラーリの模型や姫路城とかお城を組み立てたり、週刊「まんが日本の歴史」とか週刊「世界の美術館」みたいな、いわゆる分冊百科ですね。今はちょっとすたれたけど、2008年ころは、デアゴスティーニや、アシェット、小学館、講談社など複数の出版社がいろんなシリーズを頻繁に発行してました。とくに、デアゴスティーニ。もともとイタリアの地図の会社。デア社が日本に進出してきて。今もやってますけど、当時はものすごい売れてましたね。ターゲットの団塊の世代の男性たちがまだ年金生活者になる一歩手前だったと思うんです。
中野
すごいその頃、テレビCMやってました。
加藤
やってたでしょ。パートワークって、マーケティング先行型の商品で特殊ですよね。もともとデアゴスティーニは、ヨーロッパ全図の地図を、旅の目的地別、地域ごとに分けたところ大当たりした。そこから「分冊」っていう発想になったみたいね。新潟県、広島県、静岡県とかで先行テスト販売をして、売れ行きがよかったら、相当量のテレビコマーシャルを打って、そのコンバージョンも数値化して全国販売に踏み切る。テスト販売をもとに第一巻の部数を割り出し、そこから漸減していく売れ行き曲線があって、というような商品。
谷
地図を分けたことから来てるんだ。そのあと、パートワークの本は出されたんですか?
加藤
いや、『週刊現代』のときに勝間和代さんに雑誌記事をやってもらったご縁もあって、勝間さん監修のパートワークをやろうかって話になったんだけど、いろいろ考えてるうちに、その商品をパートワークに落とし込むのはむつかしいってことになって。
池田
勝間さんブームのときに。
加藤
そう、企画は、脳トレ。「囚人のジレンマ」とか「フェルミ推定」とか、勝間さんは論理パズルが大好きで、「頭をきたえる」パズルのパートワークを発想したのですが、パートワークにハマらない。勝間さんはもともと子どものころから『頭の体操』が大好きだったのね。多湖輝さんの『頭の体操』って名著があるの。いいタイトルですよね。カッパブックスという光文社の大当たりした新書のなかでもめちゃくちゃ売れた、いわゆるパズル本の古典です。それをベースにしたNintendo DSのエンターテイメントが『レイトン教授』。レイトン教授の出題するパズルの元は『頭の体操』。ものすごく、よくできてる。
中野
『頭の体操』すごいありました、実家に。
加藤
『頭の体操』読み直すとすごくよくできてて。その『頭の体操』の勝間版「脳トレ本」を、当時まだガラケーだったけど、携帯電話でさくさくパズルができる有料会員のサービスのテキストとして発売するという、紙+ネットの企画に切り替えたんです。『勝間和代の脳力UP 一日5分!「携帯パズル」でみるみる頭がよくなる!!』っていう脳トレの本。単なる紙だけじゃなく、ネットで、双方向の連動プロジェクトをやろうってことになって、ガラケーのサイトをつくったんです。
谷
へええ、その当時に、サイトを作られたんですか!
加藤
そう、そのときに、デジタルの部局に人にも参加してもらって3年間の事業計画を作ってスタートして当初はインパクトあったのですが、大成功にはいたりませんでした。サイト運営って、雑誌や本づくりとまた勝手が違ってたいへんでした。
池田
どう違ったんですか?
加藤
なんていうのか雑誌でも書籍でも、どちらかというと職人肌みたいな仕事の仕方をしてきたでしょ。編集長として売り上げ=部数はみてたけど、ネット運営というのは、そのまま独立した事業体、小さな会社の社長みたいな仕事なんです。収益性、顧客管理・対応から、ネット配信のコンテンツ……この本の場合だと配信するパズルやクイズのことですね。その品質管理から全部に目を配って「経営」することだったわけで、一介の職人としてはやることなすこと未知のことばかり。いまなら、たとえば「現代ビジネス」の編集長やマネージャーはそういうことをやってるわけで、ピンときますが、当時、自分のやっていることがよくわからなかったんですよね。
谷
事業計画を立てて……って、本当に経営者みたいですね。
加藤
コンテンツを経営することとコンテンツの開発って両方見ないとわからないでしょ。車の両輪みたいなもの。そういう意味では初めての経験なんでね。経験してよかったなと思うんですけども。それで結果としては、本はまあ売れたけど、ガラケーの課金が、なかなかうまくいかなかったんですよね。
谷
携帯と本を連動させるしくみをそのころに。加藤さんって本当にいろんなことをされてますよね。
中野
早い。時代にのってる感じですね。
加藤
っていうか、ものをじっくり考えられない、ケーソツってだけなんですけどね。
| 加藤晴之さんインタビュー[目次] |
|---|
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第1回 「撃ち込まれたんじゃなくて、銃弾が送られてきたの。封書で」 |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第2回 「白洲次郎は、チャラいイメージだった」 |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第3回 「書籍編集はボクシング。作家はボクサー。編集者はセコンド」 |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第4回 僕は、「どうしよう。こんなのみつかっちゃったけど」っていうほうです |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第5回 「作家って、こういうふうに嘘つくんだ」 |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第6回 「ええ、うちの店主が海賊なんですか!?」 |
| 【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第7回 「編集者が思った通りできたものって、それ以上伸びないよね」 |
RECOMMEND
この記事を書いた人
RANKING